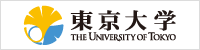ロッコ・ロンキ教授講演会
「盲目の直観―現代思想における精神分析と現象学の討論」

レポート

法政大学で毎年夏学期に開催されている「エラスムス・ムンドゥス/ユーロフィロゾフィー」プログラムでは、EUから選抜されてきた奨学生を受け入れて日仏の教員団がフランス語による哲学の講義を行っているが、CPAGでは去る4月10日、このプログラムの担当教員として来日中のロッコ・ロンキ教授を招いて講演会を開催した。
ロッコ・ロンキ教授の専門はコミュニケーション論およびベルクソン研究で、今回の来日は数年前に開催されたベルクソンに関する国際学会での講演以来二度目となる。イタリアのラクイラ大学で哲学の教鞭を執る傍ら、ミラノの応用精神分析研究所(Instituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata)において分析家に対する哲学教育を担当しているロンキ教授に、今回「盲目の直観―現代思想における精神分析と現象学の討論」というタイトルでお話しいただくことになった。
分析家、とりわけラカン派の分析家にとっての哲学的な背景知識の重要性を強調するロンキ教授だが、これは20世紀フランスの哲学と精神分析が、批判的な相互参照のなかでそれぞれ展開してきたという経緯があるからだ。哲学の側では、フロイトをはじめとする精神分析家の議論から得られる洞察は尊重しながらも、その実践には距離を取るというスタンスが目立つ一方で、精神分析の側でヘーゲル、ハイデガー、デカルトその他の哲学者を参照しながら自らの理論を構築したラカンは、哲学の認識論的な伝統には一貫して批判的な立場をとってきた。今回の講演でロンキ教授は、このラカン的な立場をいったん引き受けた上で、精神分析から哲学へと向かう道を見出そうとする。すなわち現象学でその厳密性の極点に達するような認識論の伝統―主体と対象の相関関係を枠組として人間の知を考えるような哲学の伝統―の外に位置する領域を探索しようとしているのが精神分析であるとしたうえで、この領域―フロイトにとっての「無意識」であり、ラカンにとっての「レエル」―に対応するものが、実際には哲学の議論のなかでさまざまな仕方で現れてくるのを指摘するのである。

哲学における「レエル」なものの次元としてロンキ教授がまず指摘するのが、表題にもなっている「盲目の直観 une intuition aveugle」である。カントの『純粋理性批判』の有名な一節、「内容のない思想は空虚であり、概念のない直観は盲目である」について、後半で述べられている直観、「概念のない」「盲目の」直観が、ラカンのいう「まなざし(視線)le regard」ないし「視ること regarder」に対応するとロンキ教授は指摘する。あくまで光のなかで展開し、主体に対象の像を与える「見ること voir」に対して、「視ること regarder」はそうした主体と対象の伝統的な枠組の外で生起する経験―いわゆる「欲動」の経験―を指す。「盲目の直観」はこの経験の次元を指し示すいわば標柱として選ばれており、その先に広がる、超越論的感性論を超えた経験の次元に哲学がどう対応してきたかが問題となる。
ロンキ教授が参照する事例は、ベルグソン的な純粋イマージュ―「何についてでもないイマージュ、また誰のためでもないイマージュ」―の概念であり、「それ自身で存在するイマージュの総体」としての「物質 matière」の概念であり、さらにはそれを踏まえてドゥルーズが展開した映画の「物質性 matérialisme」についての議論である。またロンキ教授は、こうした純粋イマージュの成立の場面として、フロイトの症例「狼男」の「原場面 Urzsene」を理解しようとする。フロイトが、主体が幼時に目撃したと想定する寝室の光景は、主体の内に書き込まれるが、彼がその意味を理解するのは事後的にでしかない。ここでその書き込みは、語源的な意味における「写真」、「純粋な刻印」であり、人間の手になるものではない「アケイロポイエーシス」、意識されることなく自動的に、生き生きした現在の外で遂行されている。さらにそこで成立した「何についてでもない、誰のものでもないイマージュ」「解釈者なき痕跡」は、主体の神経症的な実存を決定づける「原因」ともなっている。ロンキ教授が冒頭で指摘していた「対象 Objet」のもう一つの意味―精神分析が際だたせた、「原因」という意味―におけるイマージュが、ここには見出されるわけだ。

ロンキ教授は、結論として現象学のアポリアとしての絶対的自我の現象の問題に触れ、その超克の可能性をラカンの欲動と享楽をめぐる議論に示唆して講演を締めくくったが、その際哲学のあり方を、「見ること voir」の外の領域で「あえて(あるいは強いて)見ること la voyance」(この言葉は一般に透視術といった意味合いで使われる)と位置づけていたのが印象的であった。質疑応答では、「見ること」における光の役割、純粋イマージュの匿名性と、やはり基本的に匿名の、そして場合によっては対象をもたないとされたラカンの「シニフィアン」概念のあいだの関係、さらには「あえて(あるいは強いて)見ること la voyance」としての哲学の構想と、「哲学」をむしろ「詩作」に対立させるプラトン的な哲学の位置づけとの関係などをめぐって、長時間にわたり活発な議論が交わされた。(報告:原)