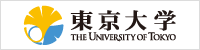【報告】 CPAG若手研究者ワークショップ 「ヨーロッパ」とその他者
2014年2月23日(日)東洋文化研究所大会議室にてCPAG若手ワークショップ:「「ヨーロッパ」とその他者」が行われた。昨年の「ジャン=リュック・ナンシー『フクシマの後で』から出発して」から第二回目の若手研究者ワークショップとなる。
冒頭、CPAG研究代表者中島隆博から挨拶があり、その後、特任研究員馬場が企画趣旨について説明をした。CPAGにはステージ1とステージ2、相補的な二つのステージがある。ステージ1における現代思想の概念マップ作成には「カテゴリー分析」と「東西比較分析」の二つがある。今回の企画は、今日のグローバル化した世界形成の大きな要因であるヨーロッパを軸に、「東西比較分析」に相当する作業を試みた。以下がその要約であるが、5本の発表を通じて、東西比較分析が単なる二つの明確に区別されたものの比較ではないことが浮き彫りになったように思われる。

第一部では馬場、片岡大右氏(東京大学研究員)、杉本隆司氏(一橋大学研究員)が主として「ヨーロッパ」にかかわる発表を、第二部では羽根次郎氏(愛知大学)、白井聡氏(文化学園大学)が、ヨーロッパの外部周辺、外部にかかわる発表を行った。
馬場は「反理論と正義――リオタールにおけるパガニスム素描」(当初告知された「リオタールとミルネールにおける異教概念」から変更)と題し、現代フランスの哲学者ジャン=フランソワ・リオタールが70年代後半に使用していた特異なパガニスム(異教)形象を扱った。
パガニスム概念は(ユダヤ・)キリスト教以外の宗教全てを指し、場合によってはギリシア・ローマ文明をも意味する概念である。基本的には宗教的な事柄に指示対象をもつこの概念は、かつてレヴィナスによって存在論的な概念として練り直された。レヴィナスの読者でもあるリオタールは、この言葉を、もはや概念ではなく一種の形象として、しかも共産主義的全体主義や資本主義を含めた抑圧的秩序に抗する、民衆のリビドー的運動を掬い上げる手がかりにしていた。発表では、本来キリスト教的ヨーロッパの他者を指すこの語が、まさにヨーロッパ自身の内部に含む他者性をくみ上げる一つの「計画的」で「論争的な」形象であることが論じられた。
この場合、「ヨーロッパ」は己の内と外に「異教」という他者を措定していることになるのだが、そもそも「ヨーロッパ」というまとまり自体が、歴史的に構成され、今日ではその政治制度的枠組みがヨーロッパ人自身によって強く問い返されている。
この決して単純ではない消息を片岡氏は発表「ヨーロッパ理念の歴史と現在」で明解に示した。「ヨーロッパ人」の起源は、およそルネサンス期までトロイアの末裔であるという神話が流通していたが、文献学的研究の広がりにより神話は崩れてゆく。その後ヨーロッパ人は己の「蛮人」としての起源に向かい合うようになるのだが、その内なる「蛮性」を決して否定しきれずむしろそこからその文明性を引き出す試みが続けられてきた。他方、ヨーロッパという呼称が流布し始めたのは、ペトラルカあたりを分水嶺としている。それ以前はRespublica christiana(キリスト教共同体)という名称が一般的だったが、東方教会や世俗権力の台頭、それによる教会権力の弱体化により「ヨーロッパ」という呼称が優性となる。今日のヨーロッパはウェストファリア条約を基礎にしており、その国家原理は国家理性である。現在のEU連合加盟国の動きからも明らかなように、ヨーロッパという理念はもはやその有効性が疑問に付されている。文明の源としてのヨーロッパという像はその起源においても現在においても実像に即していないのである。

続く杉本氏の発表「近代的フェティシズムの誕生―B.コンスタンの宗教と政治」は、フェティシズム概念が19世紀末ヨーロッパにおいて被った変容の前触れを、B.コンスタンの宗教論・政治論を舞台に探った。
ド・ブロスを嚆矢とするフェティシズム概念は当初、人類の宗教史の再初期段階にあった宗教形態(そしてヨーロッパが植民地支配したアフリカ・新大陸ではまだ続いている宗教形態)として作られた宗教学的な概念である。フランス革命後を生きた政治思想家としてのコンスタンは、社会における国家と教会のあらたなあり方を構想した。人間精神の進歩性は、人間の本源的にもっている宗教感情とどのように向かい合うべきなのか。コンスタンはフェティシズムを宗教感情の根幹にあるものとみる。それは信仰の進歩という観点からみれば、幼稚で愚鈍なものでありながらも、道徳観念を進歩させることができる、両義的なものである。人類の信仰の歴史的展開をみると、儀礼や司祭という権力構造をうまないギリシア・ローマの自由な独立多神教と司祭階級をもつ聖職多神教がある。後者は一種の専制形態である。宗教の進歩はこののち一神教へと進み国家権力と結託する。コンスタンはギリシア・ローマの独立多神教を例外としてあらゆる宗教が本源的なフェティシズムという信仰形態からの堕落であると考えた。

キリスト教の外部である異教的信仰と考えられていたフェティシズムはこうして人間に内在する自由な宗教感情の原型とされる。19世紀末にフェティシズムはヨーロッパ人の内面真理(性的倒錯)と社会体制(資本制社会)を分析する道具として、ヨーロッパ人自身に適用されることとなる。ヨーロッパ人が唾棄すべき迷信がその内部に見出だされることになる。ヨーロッパの外部から内部への移動を、コンスタンのフェティシズムへの両価的態度(幼稚でありつつ自由な道徳感情)は告げている。
以上みてきたように、「異教」は、リオタールにおいてヨーロッパ民衆がもつ社会変革の不定形のリビドーとして「ヨーロッパ」自身に適用されていること、「ヨーロッパ人」自身がその内的な蛮性を抱え込み決して否定しきってはこなかったこと、そしてフェティシズムもまた、近代においてはヨーロッパの内部に見出だされる。三本の発表が図らずも共通して指し示していたのは、理性を体現する啓蒙的ヨーロッパ精神といった像は、このようにヨーロッパ自身がつねに解体してきた、という事実である。
休憩を挟み後半の発表が行われた。最初は羽根次郎氏が「海洋中国想像による内陸中国想像への勝利について――西欧を中心とした中国呼称の系譜に関する考察」と題する発表を行った。

古代ギリシア文献から近代に至るまで、ヨーロッパの様々な文献のなかには中国とおぼしき地域を指す呼称が複数あった。絹糸の貿易を通じて間接的にその存在が知られた最初期から、その呼称には二つの系統がある。プトレマイオス以降ある程度定着したのは、内陸を通じて到達された場合は「セレス」、海運の最果ての目的地の場合は「シナイ」という二つの呼称である。その後マルコ・ポーロまでには「シナイ」には「ツィニスタ」、「セレナ」には「タウガス」という呼称が見られる。
しかし、モンゴル帝国がユーラシア大陸で勢力を得るようになると状況は複雑になる。『東方見聞録』ではセレス系統は「カタイ」(遼ないし金)、シナイ系統では「マンジ」(南宋)があり、モンゴルに対応する想像として「タ(ル)タール」が登場する。「タタール」像はその後、万里の長城以北に居住する野蛮な異民族の地と見なされる。他方明朝が統一した中国にイエズス会宣教師が訪れ、「海洋」と「内陸」の二種類あった中国想像は「内陸中国想像」(シナス)へと統一される。長城以北は、実際にはシナスの一部であっても野蛮なタタールの地と見なされる。女真族が建国した後金(清朝の前身)は元来「カタイ」とされていたのが、タタールの国と見なされることになる。
このように、内陸中国という西洋の想像は、タタールという長城以北の蛮族という想像を伴って成立した。こうした中国認識が明治政府に伝わり一方では満鮮史観へと接続し、他方では留日中国人留学生の排満運動に大きな影響を与えた。発表は後者一例として、章炳麟の文章により締めくくられた。近代初期の東アジアにおける中国認識は、西洋における中国認識の長い変遷の余波を受け、無自覚にそれを変奏しているのである。
白井氏による「ロシア・マルクス主義における〈西欧〉」では、ロシアの政治潮流における西欧派・スラヴ派の対立と、そこでレーニンが取った独特の戦略が論じられた。

発表冒頭ではレーニンへの三つの賛辞(ソレル、芥川、小林秀雄)が、共通してレーニンの東洋性(ないし土着性)に着目していることが指摘された。しかし、レーニンはむしろロシア性、土着性を強調するナロードニキ主義とは対立していた。様々な潮流を含むナロードニキ主義は、ロシアに資本主義はなじまないという信条を共有している。これに対し、レーニンはロシア資本主義はすでに発展軌道に入っている、と状況分析を逆転させたのである。こうした対立はレーニン以前の19世紀ロシアにおける西欧派とスラヴ派の対立を反復している。しかしスラヴはドイツロマン主義からの影響を受けており、またナロードニキ主義は後発資本主義国にありがちな理論を展開しており、近代化に乗り遅れた後発国に共通の反動性を示し、かならずしも特殊ロシア的とはいえない。これに対し、レーニンが目指した「原マルクス主義」は徹底して西欧派的でありながらも、ロシアの特殊事情を革命決行のために活用する。こうしてレーニンは、西欧的マルクス主義とは異なる独自のロシア・マルクス主義を生み出すことになる。
非西欧を掲げる潮流はむしろ西欧性に強く規定され、西欧性を全面に打ち出すレーニンの思考は、西欧とは一線を画すことになる。近代化に対する反動の外見上の土着性が呈する普遍性、普遍性を確保しようとする理論が結果として生み出す特殊性という逆説を、白井氏はロシアという事例に即して鮮やかに示した。
すべての発表ののち、各発表者によりお互いに質疑応答及びコメントがなされ、その後会場ともやり取りがなされた。世界史とは中国という多様な存在に蓋をする〔単純化する〕ことで成立する概念なのではないか、とは羽根氏の問題提起であった。これに片岡氏は、ヨーロッパは決して普遍的な価値の特権的な代表者ではなく、ヨーロッパ外部の人間はヨーロッパに学ぶべきことがあれば学べばよいのであって、文明の中心地として特権視する時代は終わったと応じた。

羽根氏の発表が示したように、ヨーロッパは想像された中国像をヨーロッパよりも広い地域に投影してきた、そして近代東アジアはその幻影に翻弄された。中国に長く滞在した羽根氏、ロシアに留学した白井両氏がそれぞれ指摘したが、中国やロシアに関する日本の報道には欧米よりの偏向が見られる。東アジアの近代を見渡すなら、それはいまに始まったことではないのだと言えるだろう。

片岡氏の発表が論じたように、ヨーロッパはその蛮人としての起源を抱え込み続けている。そして杉本氏が示したように、非文明的形象であるフェティシズムが近代以降ヨーロッパの内側に、ヨーロッパ自身によって発見された。おそらくリオタールとレーニンはともに理論化されざるものを、社会の可塑性を形成する民衆のエネルギーと見なしたのではなかろうか。ただし、そのエネルギーは諸刃の剣である。リオタールの異教概念がほんの数年間しか使われなかったのも、そうした事情に由来するのかもしれない。
5本の発表と討論を振り返ってみると、当初想定していた東西比較分析という枠組みに収まらない、「東西」というカテゴリー自体の自己解体がおぼろげに見えてきた。「ヨーロッパ」を問うことは、「ヨーロッパ」自身の自問自答を見届けることでもあり、「ヨーロッパ」に枠づけられたわたしたち自身の近代を見直すことでもある。今後もこうした問いかけが継続できることを願いたい。
末筆ながら、多忙のなか充実した発表を準備して下さった発表者の方々と、フロアから問いを投げかけてくれた来場者の方々には、心から感謝したい。
(報告:馬場智一)