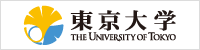“Co-existence in Asian Thought” Symposium
2014年2月3日、ミャンマーのヤンゴン大学哲学部において、“Co-existence in Asian Thought”と題したシンポジウムを行った。
名誉教授のダウ・チーチーラ先生のオープニング・スピーチでは、グローバル資本主義や、民族、信条、文化の間での様々なコンフリクトがもたらすカオス的な状況の中で、人間は脅威と危機にさらされているが、それに対して、周辺化されているように見える人文学なかでも哲学がいかにして応答し、問いを打ち立てるのかが極めて重要であることが、静かにそして力強く語られた。

続いて、小林康夫先生(東京大学教授)が、“Thoughts of Co-existence in 21st Century”と題して、以下の内容の講演を行った。すなわち、西欧からはじまるモダニティの文化は、現在の地球規模でのグローバル文化時代に至って大きく変貌し、その「限界」が問われはじめている。すなわち、個々の原理それ自体はかならずしも非人間的ではないにもかかわらず、その集積が生み出す効果はすでに人類の存在そのものを脅かす危機を産み出している。この危機的限界線に閉じ込められた閉塞性をいかに、どのように突破して新しい「共生」の地平を拓くことができるかをいま、哲学は問わなければならない。そのためには、このグローバル文化を構成する主要な諸次元(1)科学―技術―産業、(2)資本主義(自由市場)、(3)デモクラシー,(4)芸術(個人による自己表現)、そしてそれらを綜合するものである(5)歴史の主体としての人間(個人)などについて、ある種の批判的なディコンストラクションを行う必要がある。そのとき、ひとつの可能性として、ミャンマーに伝わるいわゆる上座部仏教の倫理性に注目することができないか。仏教の教えの根幹にある、自我を構成されたものとして理解し、その構成そのものをディコンストラクトするプラクシスは、モダニティの根本倫理である「自由なる個」の限界を超えて根源的な「共生」、すなわち、自と他とのあいだの「共生」ではなく、自そのものが根源的に、アプリオリに「共生的」であるという存在論的「共生」への路を指し示してはいないか。この「路」をここではparticipationの存在論として捉え、そこから出発して新しい実践的な「共生」の世界観へと向かうことをミャンマーの研究者たちとともに考えたいと思う。
この提題に対して、名誉教授のダウ・チーチーラ先生を筆頭にミャンマー側の参加者から鋭い質問が寄せられた。とりわけそこで「デモクラシー」原理すらもが批判的に捉えられることに対して疑義が呈されたが、「デモクラシー」が選挙という制度を通じてのmajority によるminorityの支配の正当化につながる一面をどのように乗り越えて、つねに来るべきものとしての「デモクラシー」を構想することの重要性などについて討議が行われた。また、講演タイトルが「アジア」という限定をつけていることに関しても質問が寄せられた。
二番目の講演は、中島隆博(東京大学准教授)による“Philosophical Network of Co-existence in Asia: Challenges of UTCP and CPAG”であった。ここで中島は、UTCPの10年間とそれに続くCPAGの2年間において、アジアの研究者たちといかなるネットワークを築き上げ、そこにおいていかなる問いを共有してきたのか、そしてその意義は何かについて論じた。焦点は二つあり、一つは自然との共生、もう一つはアジアとの共生である。自然との共生に関しては、福島原発事故を受けて、わたしたちが従来有している科学に対する想像力では到底それを捉えきることができず、新たな社会的想像力が求められていることを論じた。また、近代において植民地と戦争を通じて関わったアジアとの関係は、今日でも政治的な焦点になるほど複雑であるが、そのアジアとの共生をともに構想することが長期的にも短期的にもきわめて重要であることを論じた。後者の例として、韓国・台湾・中国・シンガポール・香港そしてオーストラリアの研究者たちとの長く密度の高い交流を挙げ、それをCPAGが継承し発展させようとしていることに触れた。ポイントは、地域的で特異である問題が、同時に普遍的であるように思考する態度をいかに共有するか、また他者への想像力をいかにして繊細なものにしていくのかが、アジアとの共生においては肝要であるというものである。
質問がいくつか寄せられたが、その中で自然との共生のための社会的想像力を養うために、伝統文化をどのように組み込んでいけばよいのか、というものがあった。近代を経ている以上、伝統文化をそのまま適用することは難しいにしても、地域的なスピリチュアリティを再構築するためには、何らかの仕方で(たとえば批判的に)伝統文化を継承することができるのではないだろうか。また、アジアとの共生に関しては、やはりアジアだけに限定されるべきではないとの質問があった。ここにもアジアと近代の問題が繰り返し現れているように思われた。

午後は、井戸美里(東京大学助教)と沖本幸子(青山学院大学准教授)の日本文化に焦点を当てた講演と質疑であった。美術や芸能研究の現場から「共生」について考察しようとしたもので、両者の講演の共通の問いは、’liminality’ (境界性)という概念が日本の文化について思考する際にどのような意味を持っているのかという点であった。
井戸美里は、「美術と儀礼-日本美術における一時性と境界性」と題して、一般に常設の壁掛けのタブローを想起させる「絵画」や「美術」という概念が、前近代の日本美術を語る際にはいかに特殊なものであるかということを、必要なときにのみ観賞される大画面絵画の存在を例に指摘した。明治期以前の日本において大画面の「絵画」といえば、軸物(掛け幅)や障子絵や屏風であり、崇高な「美術」というよりは、むしろ建築の一部として日々の生活や年中行事、さまざまな儀礼の場に溶け込みながら室礼として使用された。実際、仏教の行事などの際には、涅槃図や社寺の由来を描いた縁起絵などの掛け幅などは、多くの人々が共有することのできる一回限りの儀礼空間を創出していた。また、屏風の場合は、出産、葬送、芸能などの儀礼の場に立てられることも多く、世俗との結界として境界的な場を作り出すことができる装置である。興味深いのは、結界として立てられた屏風によって囲われた場が、世俗的な秩序からのアジールのような空間を一時的に仕立て上げていたことであり、とりわけ金屏風のように非日常性を演出することのできる屏風が適していたと考えられる。臨終や葬送のみならず、茶の湯や連歌などの空間に金屏風が運び込まれたことも、日本の芸能の持つ一回性の境界的な空間を立ち上げることができたからであったと思われる。階級やジェンダーを超えて立ち入りが許可されていた芸能の場は、原理上は共生の実践の場としての無縁の空間であり、そうした場に美術が果たす役割を指摘した。
沖本幸子からは「死者との共生-日本の芸能における境界性」と題した報告があった。生者と死者、あの世とこの世の境界が芸能の中にどのように構造化され、どのような共生の思想を身体に刻みこんできたのか。現在でも日本全国で踊られている盆踊りのルーツ「風流踊り(ふりゅうおどり)」に焦点を当てながら考察していった。注目したのは、1:「風流」という美意識、2:「踊り」という行為についてである。まず、「風流」という美意識について。趣向を凝らすという意味の「風流」という概念が、民衆の芸能に入って奇抜さを競うものとなり、日本では、祝福ではなく鎮魂の芸能が華麗なものになる要因となったことを説明。「風流」の趣向は、仮装の形で顕著に現れたが、そうしたものが死者の霊魂を惹きつけ、もてなす役割と同時に、たとえば顔を隠しアイデンティティをなくすことで、死者との交わりから身を守る役割が期待されていた可能性を指摘した。次に、「踊り」という行為について。踊りが、死者と一体化し死者と共に踊るという死者を深くもてなすものでありつつ、ある意味危険な行為である一方、あの世に送り返す力のある行為として捉えられていたことを指摘し、お盆で迎えた死者たちを送り返すために、なくてはならない存在だったことを指摘した。すなわち、「風流」も「踊り」もあの世とこの世の境界に立つための手段だったのである。
そして、年に1度行われる「盆踊り」が、死者と触れ合う時間であると同時に、生者たちにとっても恋が生まれる何よりの楽しみの場であったことに触れ、死者と共に生きることによって未来が祝福されるというあり方、さらに、輪になって、アイデンティティを隠して踊ることで、あの世とこの世の境界を自らの身体を通してその場に現出させ、死者と共にあることを身体に刻み込んでいくというあり方に、「盆踊り」における「死者との共生」の知、身体の知が見られるのではないかとした。最後に、言語化された哲学だけではなく、身体に刻み込まれた知を発掘していくことの重要性を説いてしめくくった。
二人の講演を受けて、小林、中島両氏がディスカッサントとして登壇した。井戸の指摘した屏風と、沖本の取り上げた盆踊りの輪が同様に境界の役割を果たすことに触れながら、「境界」の向こうの「死者」が身近である日本文化にとって、死者は他者として日常から切り離すことのできる存在ではなく、人々の日常生活のなかに何らかの形で「共生」していたこと、芸能はまさにこうした「境界性」において出現するものであり、美術も死者の世界の境界を作り出すメディアとして存在していたことを指摘した。
これに対してダウ・チーチーラ先生は、「死者との共生」という言葉自体は理解できるとしながらも、しかし、ミャンマーの近代史を振り返るとき、その概念は必ずしも簡単に受け入れられるものではないとした。アジアの近代の中で、お互いの立場をどのように乗り越えながら普遍的な知を探求していくのか。極めて困難な課題だが、日本の様々な失敗を謙虚に具体的に見つめ直し、共にアジアの未来を構想していくことの重要性も再認識させられた。
最後に、このシンポジウムが可能になったのは、ひとえにレレウィン先生(ヤンゴン大学教授)の御尽力である。そして、このシンポジウムを哲学的に密度の高いものにしてくださったのは、名誉教授のダウ・チーチーラ先生であった。先生がヤンゴン大学で哲学教育を受けていた学生時代のお話を伺ったが、錚々たる教授陣のもと、良質の教育がなされていたことがよくわかった。この会場には多くの中堅の哲学の先生方がいらっしゃったがそのほとんどはダウ・チーチーラ先生の教え子であるとのことであった。また、昨年から二十数年ぶりにヤンゴン大学に学部生が入学してきたとのことで、高校を卒業したばかりの学生が数多く出席してくれていた。その多くは女子学生であったが、彼女たちこそがこれからの哲学の希望であることは言うまでもない。
なお、翌日、2月4日には、ミャンマーの日本大使館に勤務されていて、ミャンマーの民族文化を研究されている兵頭千夏さんと意見交換をすることができた。軍事政権下を含んで、20数年にわたってミャンマーと関わり続けていらっしゃる兵頭さんのお話には多くのことを啓発された。またもうお一方、国立民族学博物館の田村克己先生にも特筆して謝意を表したい。事前に伺ったミャンマーのお話が大変役立ったばかりか、先生自ら細やかな配慮をしてくださり、わたしたちがミャンマーに触れ、今後哲学的な問い結晶化させる手掛かりを多く得ることができた。ありがとうございます。

(報告:小林康夫、中島隆博、井戸美里、沖本幸子)