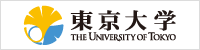ピエール・ブリュノ氏講演会「幻想、欲望、および法」報告

左より 立木康介氏、ブリュノ氏、原和之氏
さる10月25日(金)、東京大学駒場キャンパスにて、ピエール・ブリュノ氏講演会「幻想、欲望、および法」が開催された。東京大学CPAGの原和之が司会をし、京都大学人文科学研究所の立木康介氏と青山学院大学総合文化政策学部の福田大輔氏に通訳としてご参加いただいた。

福田大輔氏
ブリュノ氏はトゥールーズ第二大学、ついでパリ第八大学で1999年まで教鞭をとられた大学人であり、精神分析家としては、エコール・ドゥ・ラ・コーズ・フロイディエンヌ(Ecole de la Cause freudienne)で数々の職責を果たしたのち、2001年にジャック・ラカン精神分析協会(Association Psychanalyse Jacques Lacan)を二名の同僚とともに創設し、以降、現在まで同協会に所属しつつ活躍されている。単著でものしたLa passe (2003)、 Lacan, passeur de Marx (2010)、Une psychanalyse, du rebus au rebut (2013) などの他、Manifeste de la psychanalyse (2010) をはじめとする多数の共著を発表し、Barca!誌やPsychanalyse誌の編集長を務められるなど、著述面でも精力的な活動を展開なさっている。立木氏の招聘により実現したこのたびの来日では、最初の訪問先である京都大学で「症状、主体の分裂、資本主義のディスクール」について論じられ、東京大学にはその翌日に別の題目を携えてお越しくださった。
今回の講演の中軸をなしていたのは、ラカンの「カントとサド」(1963年)とフロイトの「子供がぶたれる」(1919年)の読解である。講演の題目を逆方向になぞる形で展開したブリュノ氏の読解は、広く思想史のうちに求めた文脈のなかで「法」の問題を提起し先鋭化させて「欲望」の問いを導入し、さらに、(フロイトによれば欲望が上演される場である)「幻想」に示唆されている神経症的なもののうちの倒錯的なものの謎へ、また「幻想」の解体という問題へと踏み込むものであった。ブリュノ氏がテクストを読み解くなかで喚起した問いや概念ないし概念的装置の主要なものを書き留めるならば次のとおりとなる。
まずラカンの注釈を参照しながらブリュノ氏が浮き彫りにしたのは、普遍的立法をめぐる言説と切り離し得ないものとしての快原理の彼岸という問題である。カントは『実践理性批判』において「汝の意志の格率がつねに同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」という定言命法を呈示しているが、この定言命法から引き出される普遍的な価値にもとづく道徳法則の対象、すなわち「善(das Gute)」は、自己愛や利害関心などの病理的な(pathologique)顧慮の一切を免れて快原理の彼岸に位置づけられる。サドの『閨房の哲学』の核心をなすのは、「我はお前の身体を享楽する権利をもち、そしてその権利を行使するだろう[…]と誰もが私に告げてよい」というやはり普遍的立法として打ち立てられた格率であって、そこでいわれている享楽への権利もまた、拷問の執行者個人の好みや情熱など利益関心に基づくモティーフを越えたところで行使される。ただしこの二つのテクストは示差的な特徴を示しており、すなわち、カントにおいて格率は〈他者〉から主体に差し向けられており(「汝の意志の格率が[…]ように行為せよ」)、「善」は理性によって到達不可能な「もの自体」のように位置づけられているが、それに対してサドでは、他者が格率を課することを主体が許しており、拷問の執行者の「そこにあること=現存在(Dasein)」が問題になりうるのである。

サド的幻想についてラカンが提案する二つのシェーマは、(「拷問の執行者」に相当する)対象a、棒線を引かれた主体、素の主体、享楽への意志という四つの項と、それぞれ欲望と錐形と呼ばれる二つの記号からなる。そのうち最初に呈示される幻想の静力学と呼ばれるシェーマは、幻想における主体と対象aの関係性を幻想のマテームによって示し、また、快原理に服従する主体と、享楽への意志によって分割された、つまり〈他者〉の享楽の道具へと還元されかねない(快を断念した)主体という、カントにおいても示唆されていた主体の二つのあり方をすでに明示している。しかしながら、九〇度回転した形で次に呈示される幻想の動力学と呼ばれるシェーマは、(疎外の時間における消失を経た)分割された主体の上に欲望が直接的に作用することを示し、すなわち主体が欲望する可能性を標すにいたっている。だが同時にこの幻想の動力学は、まさしくサドが遺言で自らの墓碑へ名を残すことを拒み自らの完全な消滅を願ったように、「生まれなかったこと」の勝利を示唆するものであり、純粋ないし裸の欲望が一つの行き詰まりであることを告げている。
「子供がぶたれる」でフロイトは、複数の神経症の患者によって報告され、彼らの自慰的満足の下敷きになっている父による打擲を中心に展開する幻想について「倒錯の最初の特徴」(サディズム的あるいはマゾヒズム的特徴)を指摘している。ラカンのシェーマに照らし合わせるならば、一人の子供がぶたれる、あるいは私がぶたれることを欲望する〈他者〉を、また、起源的に〈他者〉において先取りされたものとしての対象aをここで問題にしうるのであり、幻想によるかぎり主体は「〈私〉は欲望する」を引き受けられないことをあらためて強調しうるのである。分析治療においては、現実的な父の形のもとで幻想の執行者としての対象aを摘出することで「幻想の横断」が標される。(ファルスの法の例外をなす)現実的な父の核が取り出されるところにおいてこそ幻想の解体が可能になるのである。
ブリュノ氏の最後のテーゼは、フロイトのテクストとラカンのテクストとさらにブリュノ氏の実践から出てきた言葉とを重ね合わせるものであった。上では省略したが、カントやサドの著作の執筆時期がフランス革命期に対応することに注意を喚起したり、精神分析の倫理がカント的あるいはサド的コンセプションでは十全に根拠づけられないことを指摘したりするなど、講演を通じて氏がテクスト外の文脈を絶えず考慮していたことも印象的であった。また氏が聴衆の様子に応じて柔軟に対応し、質問を受けて解説を付け加えていたこと、そしてそうしながらも見事な手際で議論を収斂させ聴衆を結論まで導いたこともここでとくに記しておきたい。
講演後の質疑応答では、超越論的な性格をもつラカンのテクストとフロイトの臨床的なテクストの分節、ラカンにおけるサディズムとマゾヒズムの関係、フロイトにおける享楽の問題の所在などの論点がとりあげられた。限られた時間のなかでのことではあったが、含蓄あるやりとりを聞き、ブリュノ氏の思索のさらなる深みをかいま見ることができたのは大きな幸運であった。
報告:佐藤朋子