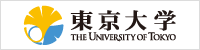(Im)possible Queer International Feminism

レポート
2013年5月17日から19日にかけて、英国Sussex Universityで開催された(Im)possibly Queer International Feminismsは、International Feminist Journal of Politicsが後援するフェミニスト政治学や国際関係論を中心とした学会であるが、今回はフェミニズム国際政治論にクィア・ポリティクスをいかに接合するのかをテーマとして、アフリカ大陸や中南米、西・南アジアを含む各地の研究者が集って活発な意見交換が行われた。
学会の性質から予測されたことではあるが、現在のクィア・スタディーズで最大の関心領域のひとつである「ホモナショナリズム批判」に関する報告の多さは際立っており、「ホモナショナリズム批判」が、もともとこの用語が提示された米国の〈対テロ戦争〉やそこから拡大された英米をはじめとする西欧諸国におけるイスラモフォビアや移民排斥とセクシュアリティの政治との関係という文脈は言うまでもなく、中南米や旧東欧諸国までふくめ、国際政治とナショナリズム、そしてセクシュアリティの政治との緊張に満ちた共犯関係を分析する際に広く共有される枠組みとなっていることが、あらためて実感された。
しかしこれは他面では、「ホモナショナリズム批判」のこのような広がりの問題点を浮き彫りにする効果も持っていたように思われる。
ひとつには、J.Puarが〈対テロ戦争下の米国〉という特定の文脈において提示したこの枠組みが、〈西欧〉におけるイスラモフォビアと排外主義の隆盛の分析においてきわめて強力であったために、逆に個々の事例における国家間の政治、国内での「国家主義」的な政治、そしてセクシュアリティの政治とのそれぞれ特異な緊張関係が、「ホモナショナリズム」の一語で片付けられるケースが見られたことである。まさしくそのために、異なる文脈におけるセクシュアリティの政治の分析が多様さを欠く結果となり、期せずして、まさしくPuarの分析が可能性としてもっていた既存のクィア理論とポリティクスにおける米国中心主義が、米国の分析枠組みを他地域にそのまま再導入するという形で再生産されてしまう危険があるのではないか、と思われた。
さらに、このように米国の文脈に基づく特定の分析枠組みがあまりに無批判に流用され、領域における一種の「ブーム」となることが、皮肉なことに、「ホモナショナリズム」というこの特定の分析枠組みにうまく合致しないような分析や考察を領域からあらかじめ締め出す効果を持つのではないか、という点も懸念される。「ホモナショナリズム批判」がもっとも有効に機能するのは、当然のことながら、米国(あるいは米国と一部西欧諸国、そしてイスラエル)におけるセクシュアリティの政治とイスラモフォビアとが分析対象となる場合である。したがって、たとえば今回のような国際政治系の学会においてこの枠組みがはじめから特権的な地位を占める場合、これらとは異なる対象の分析に基づく考察は、そもそも議論のアリーナに入ってきにくくなる可能性があるだろう。
これらの問題点は、実際に、中南米や旧東欧諸国において研究を進めている参加者からも指摘されており、今後のクィア・スタディーズが長く批判されてきたその「英米中心主義」に対応する際に、忘れてはならない観点となるだろうと予想された。
また、学会キーノートスピーチの最後の講演者として最終日に登壇したNYUのLisa Dugganは、聴衆の期待を裏切らない鋭い分析で、現在のアメリカ合衆国におけるネオリベラルな情動を支えるイマジネーションと、セクシュアリティの政治を支えるそれとの共通点を指摘し、クィア・ポリティクスを含む現代のセクシュアリティの政治への批判を展開した。上に述べたような学会全体の傾向に照らし合わせた時に興味深いのは、分析対象をあくまでも現在の合衆国の政治的情動に明示的に限定して展開されたDugganの批判が、Queer International Feminismsの不可能性(Impossibility)をもっとも感じさせないものだった、という事である。

右が主催大学であるSussex Uni.のCynthia Weber教授、左がNYUのLIsa Duggan教授
私自身は、Reconsidering Locality and Regionalities in Queer Politicsというパネルにおいて、沖縄を中心に活躍する女性アーチストである山城知佳子の作品分析を例に、クィアネスにおける接触と隣接性の問題をポストコロニアリズムなジェンダーの磁場と接続させる考察をおこなった。東アジアおよび東欧についての報告からなるパネルであったため、クィアな問題関心に加えてポストコロニアルな観点が報告者、聴衆ともにある程度共有されていたことは、幸運であったと思う。
(報告:清水)