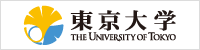日本哲学会第72回大会一般研究発表
ユダヤ哲学の方法論としての無限判断

レポート
20世紀の西洋哲学の展開を見た時、多くのユダヤ系思想家の存在なくしてその全体像を描くことはできない。しかし様々な「ユダヤ系」思想家の間を貫くなにか本質的な「ユダヤ性」なるものを見出だすのは容易いことではないし、本質主義的な陥穽がそこに控えていることもまた明らかだ。ユダヤ思想と一口に言ってもそこには、特定の主張に還元できない多様性があり、それは「西洋哲学」のなかに諸子百家が見出だせるのと同じである。
この事情を鑑みた上で西洋哲学とユダヤ教の関係を歴史的に振り返ると一体何が言えるだろうか。確かに中世哲学史にはユダヤ人哲学者マイモニデスの名が必ず見出だされるし、近世では破門の憂き目をみたスピノザがおり、現代では「ユダヤ系」の哲学者として、ベルグソン、フッサール、レヴィナス、デリダ、アドルノがおり、分析系でもパトナムの名前が挙げられる。しかしこれらの固有名に結びつけられるその思想を「ユダヤ哲学」と名付けることは可能だろうか。各々の思想形成を歴史的に精査するなら、そこにユダヤ教の何らかの伝統が直接的に継承されているのを見出だすのはほとんど不可能である。また、敢えてそのような無理な作業をする必要も感じられない。
戦後タルムード講義を続けたレヴィナスでさえ、哲学者としては特に「ユダヤ的」な概念を明示的に導入して独自の哲学を打ち立てた訳ではない。とはいえ、上に挙げた哲学者のなかでとりわけレヴィナスは、タルムードを通じてユダヤ教の伝統を意識的に継承しているのは確かだ。では、中世ではどうか。マイモニデスはアリストテレス哲学とユダヤ教を調停しようとしたことで知られる。その意味ではダヤ教の哲学者といってもよいだろう。実のところレヴィナスは、戦後にタルムード解釈を始める前に、すでに一九三五年にマイモニデスについての短い文章を書いている。ところがレヴィナスの受けたユダヤ教教育にも、それ以外の中等・高等教育でも中世ユダヤ教哲学について講じることのできた教師はいない。三〇歳そこそこのレヴィナスに中世ユダヤ教哲学についての正確な理解を伝えることができたのは、伝記的史実によるならば、全イスラエル同盟の同僚だったジャコブ・ゴルダン(Jacob Gordin)を置いて他にいない。
ゴルダンはレヴィナスのマイモニデス論の前年に書いた自身のマイモニデス論の末尾の注で、西洋哲学を「キリスト教的方向性」と「ユダヤ教的方向性」に分け、近代哲学ではカントやヘーゲルに前者の方向性を見出だし、ヘルマン・コーヘンに後者を見ている。ゴルダンのこうした大胆な哲学史的見立ては、一方では、ナチズムを逃れ一九三四年にパリやってきた後におそらく知ったであろう、「キリスト教哲学」研究としての、ジルソンによる中世哲学史に影響を受けている。しかし他方では、ベルリンのユダヤ教学研究所在籍時に出版した博士論文『無限判断の論理の探求』(1929)のなかにすでにこうした大胆な見立ての背景を見ることができる。
西洋哲学の「ユダヤ教的方向性」の具体例を、博士論文にさかのぼって探ってみると、そこにはやはりマイモニデスやコーヘンが見出だされ、その中心にある論理が「無限判断」なのである。しかしこの博士論文は、ユダヤ哲学に固有の論理を打ち立てるのを目的としているのではない。無限判断の論理が哲学体系の原理として確立されるのはヘルマン・コーヘンをまたねばならないが、その萌芽はすでに古代ギリシアにまで遡り、プラトンの存在の彼方もまたこの系譜に属す。マイモニデスはコーヘンに先駆けてこの論理を自らの哲学の方法の一部としたのであったのだが、同じ中世でもドゥンス・スコトゥスもまたこの系譜に属しているとされる。その意味では、仮にこの論理がユダヤ的方向性を形成するとしても、同種の論理が見出だされるのは、ユダヤ系の哲学者に限定されるのではないわけだ。西洋哲学の歴史上さまざまな仕方で断続的に扱われてきた無限判断の問題を、自らの哲学的方法のなかに主題的に取り入れている哲学者がマイモニデスやコーヘンだ、ということになる。
他方、キリスト教的方向性の論理はなにかというと、ゴルダンはジルソンに倣い、トマス的な存在の類比であるとし、ヘーゲル弁証法もまたその一ヴァリアントに過ぎないとする。先ほど触れたマイモニデス論(1934年)の注での大胆な哲学史的見立ては、博士論文で詳述していた、西洋哲学史上に散見される無限判断の様々な萌芽を捨象した上で成立しているに過ぎない。そしてこの捨象を促したものとして、トマス主義に基づいたジルソンの研究があると言える。
***
去る5月12日、日本哲学会第72回一般研究発表で「ユダヤ哲学の方法論としての無限判断」と題した発表をしてきた。報告者は、レヴィナスと西洋哲学の関連についての研究をするなかで、レヴィナスの同僚であったジャコブ・ゴルダン(Jacob Gordin)のユダヤ哲学史の構想に遭遇し、ゴルダンが残した草稿などを調査しつつ、近年その構想の再構成を試みている。上に述べた消息は、この研究のなかで少しずつ明らかになってきた成果の一部である。
レヴィナスが『全体性と無限』で展開した哲学史批判は、西洋哲学の歴史を〈同〉による〈他〉の還元の歴史として糾弾するものであるが、本書はその批判だけに留まらず、全体性を形成する西洋哲学の論理に対して、全体性の外部を確保する方途を探っている。今回の発表では、このようなレヴィナスへの展開も見据えつつ「無限判断」の論理の概要と、ゴルダンによる哲学史的な位置づけと問題点を検討した。
「無限判断」概念のエッセンスだけを述べれば以下のようになる。
AはBであるという単純な形式をもつあらゆる判断の根源には、AやBの定立が先行している。主語となるAはその定立においてAではないもの(非A)の無制限の排除を前提し、Aの述語となるBはAの述語として共約不可能なあらゆる述語(非B)を述定可能な領域から無制限に排除する。無制限の非A領域の虚無化(Vernichtung)はAの同一性を確立し、非Bの排除を可能にする。こうしてAの同一性とBの可能領域が確立し、AはBであるという判断が成立する。しかしある任意の述語B(1)はB(x)の領域のなかの他の述語B(2)によって取って代わられる可能性を有する。Bはつねに別様でありうる(Andersheit)。
あらゆる特定の判断には、こうした「Aではないもの」や「別様のB」という潜在的な無限の他性が伴っている。判断一般には従って常にその判断が定立する同一性の条件として他性が付随しているのである。ゴルダンはコーヘンが『純粋認識の論理学』で打ち出したこうした根源の弁証法を、存在の類比の論理の延長線上にある全体性を形成するヘーゲルの体系の弁証法よりも根源的な弁証法であるとする。レヴィナスはゴルダンに捧げた小論のなかで、ゴルダンによるコーヘンとヘーゲルの対比に触れているが、『全体性と無限』におけるある種の無限概念はこうした認識論的な論理の倫理的拡張であると思われる。
今回の発表ではこうしたレヴィナス解釈には踏み込まず、「ユダヤ哲学」という方法概念とゴルダンの無限判断を詳述するに留めた。会場からは中世キリスト教思想の大家の方から、「ユダヤ哲学」という範疇に関するコメントを頂いた。それによれば、「ユダヤ哲学」なるものが存在すると考えるには二つの方法がある。一つは「ユダヤ哲学」が歴史的に存在したと考えるもの。もう一つはある特定の角度から「ユダヤ哲学」なるものを構築する場合である。質問者の方によると、歴史的にみて「ユダヤ哲学」なるものが存在するとは言えず、言えるとすれば今回の発表のような特定の視角から構築するほかない。測らずも、今回の発表の形式上の手続きに賛同を得た形になった。コメントをして下さった会員の方にはこの場を借りて御礼申し上げたい。
しかし、今回の発表ではいわゆる行為の属性の論理についてはほとんど触れることができず、また発表者がどのような中期的計画に基づいているのかについても説明が不十分であった。行為の属性は、マイモニデス哲学のいわば倫理的側面に直結しており、存在論に対する倫理の優位と唱えるレヴィナスにもその遠いエコーを見出だせる。ゴルダンの見立てでは存在の類比(トマス)から体系の弁証法(ヘーゲル)といういわば存在論的な系譜が打ち出されているのであるが、前述の質問者の方によればトマス思想にもこうした実践の次元が存在する。
本研究は、西洋の内部に存在する伏流のようなユダヤ思想の現代的展開をユダヤ哲学として再構成し、現代西洋哲学における脱構築的運動の一部を解明しようとするものである。西洋内部の他者であるユダヤ思想は、決して特権的な資格をもったものではなく、キリスト教思想もまた、その内部に複数の思考を有している。今回の発表ではこの視角がもつ可能性の輪郭(それは同時に限界でもある)が多少とも浮かび上がったのではないかと思う。この研究に関しては中期的な展望も含めて今後も継続して報告をしてゆきたい。
(報告:馬場)