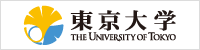UTCP共催
「Religion, Secularity, and the Public Sphere in East and Southeast Asia」

レポート
1 信仰の物質性
「信仰」は内面にかかわる問題であると同時に、目に見える「もの」を媒介にされて共有されるものでもある。磯前先生の報告で紹介された石巻の地蔵などは、まさに信仰における物質的なものの力を示す典型的な事例であるといえる。地蔵にお供えをしたひとりひとりの行為はきわめて私秘的な願いにもとづくものかもしれない。しかし、その地蔵が公道のわきに置かれていて、また、通りかかった人々がそれを見ることができ、そこに人々がお供えをすることができ、それを写真に撮る人がいて、それをめぐってシンガポールで議論をする人がいて、それを通して被災者の人々の痛みに思いをめぐらすことができる(かもしれない)というのは、やはりそこに「信仰」が目に見えるかたちで示されているからなのではないだろうか。そういった信仰の物質性は、もしかすると、中島先生が討議のなかで指摘した市民教育としての儀礼の可能性といったことにつながってくるかもしれない。
2 共同体における公共をつくりだすための外部
いくつかの報告(おもに文化人類学的な村落研究)が共同体のなかに公共性を生みだすうえで宗教的な要素が果たしている役割に注目した点が興味深かった。たとえば、中国の村落共同体を復興するためにつくられた新しい官製の文化施設に人々が寄り付かず、かわりに修築された寺院が集会所の役割を果たしていることを示した Liang先生の議論は、人々のコミュニケーションの場をつくりだすうえで「聖なるもの」が果たす役割について考えるヒントを与えてくれる。他方でコミュニケーションの場を作りだすための契機は、必ずしも宗教的な要素である必要はなく、場合によっては、共産党とか、外国援助団体の存在といったような、世俗的な「外圧」であることもある。これらのケースを慎重に分析・比較することは、村落共同体研究として意義をもつだけでなく、国家という公=共と「聖」「俗」の関係を考えるうえでも有意義であるように感じられた。(報告:加藤)
今回のシンポジウムにおける焦点の一つは政教分離及び政治と宗教の関係であり、例えば中国やカンボジアのような社会主義国、フィリピンのようなカトリック教徒の多い国、インドネシアやマレーシア、あるいはトルコのようなイスラームの強い国など、様々な文脈における政治と宗教との関係が取り上げられていた。この点は単に宗教を考えるのみならず、近代国家そのものを考える上でも大きな論点である。というのは、これらの発表を聞いていても、近代国家は自らを国家として成り立たせる際に宗教を(何らかの形で)排除し、かつ宗教に対して一定の規律をかける権力を持つこと半ば自明の前提となっているが、本当のところなぜ近代国家が宗教を規律する権力を持つのかは必ずしも明らかではない。近代国家を考える際にも、このような点を考えなくてはいけないだろう。(報告:清水)

今回の発表者は大別して、文化人類学とその他の分野に分けられるが、文化人類学の方々の発表を聞いた感じでは、イスラーム系のトルコにしても、カトリック系のフィリピンにしても、或いはベトナムなど他の宗教の影響が強い国々にしても、信仰はやはり近代国家における重要な問題として存在していることが明らかであり、決してマルクスの言ったように、「宗教は民衆へのアヘンである」と簡単に片づけられるものではなく、或いは啓蒙運動の「敵」として一蹴できるようなものでもない。その現代社会において発揮されうる精神的な役割が相変わらず非常に重要であることが、今回のシンポジウムを通じてもはっきりしている。
私が最も関心を持っているのは、中島先生も「近代日本哲学における宗教と国家」という発表で触れられた問題で、すなわち、近代国家における宗教の役割の問題である。国家と宗教はどういう関係を築くべきか、これは丸山眞男の先生南原繁も挑んだ課題であり、丸山は戦後啓蒙のために、鎌倉仏教のような日本の伝統的な宗教資源も利用しようと考えていたが、もっと突っ込んで考えると、宗教は世俗の政治にどこまで介入すべきかをめぐっては、彼は必ずしもシステマティックな説明をしたわけではなかった。リベラル・デモクラシーの政体においては、政教分離が大前提となっているが、実際、聖俗が混在している日常の中で、宗教の分野と政治の分野、必ずしも截然と分かれているとは限らないところがある。動的な関係なので、政治の力による不必要な介入へのチェック機能を果たすと同時に、政治への過度な影響をどう防ぐか、なかなかに微妙な問題である。一種の鋭い現実感覚と高度な政治的判断が求められる難しい作業でもある。そういう意味では、イギリスやフランスなどの宗教と政治の関係が一応うまく確立している国々からはまだ見習うべきところがあるだろう。今後の政治哲学の重要課題の一つとして、引き続き考えていきたいと思っている。(報告:王前)

今回のシンポジウムに参加して強く印象に残ったのは、理論研究と実践研究がお互いにどうやって接触し、接地点を探っていくか、という試みを繰り返す中にこそ、学問の新たな発展可能性が潜んでいることを肌で感じたことである。
中島先生のご発表にあった近代日本哲学における宗教と国家の位置づけにはじまり、ハンナ・アーレントに見る近代ヨーロッパの公共圏、王前先生の丸山眞男と聖俗関係をめぐる議論に代表される哲学研究に対し、清水剛先生の日本の宗教団体が法人格を与えられていくプロセス、加藤敦典さんのベトナムの墓をめぐる人々の信仰と国家の関与、イスラーム金融に対する国家の介入、雲南省におけるエスニックと宗教実践をめぐる境界の問題などはまさに、いわば「地上戦」とでも形容しうる実践研究であった。宗教と国家の関係性、そこに公共圏がどのように生じるのかという問いを、いかにして現実社会で起きているさまざまな事象に当てはめ、それからはみ出すような部分をどのように包摂していくのか(あるいは包摂できないものをどのように扱うのか)、という今回のシンポジウムの論点の一つは、「公」と「私」という一見アンビバレントに見えるものが、実際には複雑に重なり合い、時に相互補完しあいながら、さまざまな要素を持つ人々が入り混じって生活する共生社会を創り上げていくプロセスとも密接に関係する。今回のシンポジウムで繰り広げられたさまざまな議論は、この点においても、刺激的かつ有意義な内容であったと考えている。
また、世代や国を超え、学問の枠組みを超えた 30 名を超す東アジア、東南アジア研究者が、2日間、朝から晩まで一つの会場に缶詰になってすべての議論に参加し、自由にコメントをしあうという今回のシンポジウムのスタイルは、学会形式とはまた異なる緊張感とスピード感を有し、個人的には肝の縮む思いの連続ではあったが、それだけに非常に実り多い国際研究交流の場であった。今後の継続的展開を強く望むところである。(報告:伊藤)